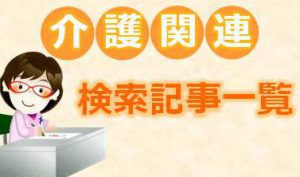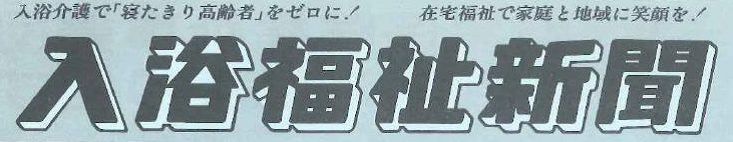
『入浴福祉新聞 第86号』(平成16(2004)年1月15日号)より
過去の入浴福祉新聞に掲載された記事をご紹介します。
発行当時の入浴や福祉等の状況を少しでもお届けできたら幸いです。
[訪問入浴サービスと感染予防]最終回
感染症の入浴介護利用者にも適切な対応を!
[入浴介護の衛生管理]をかなり早くから研究テーマとして取り組まれてきた茨城県立医療大学の小池和子教授が、デベロ老人福祉研究所の主催する「全国入浴福祉研修会」で参加者アンケートを行ったことがあります。
その結果、入浴介護に従事している7割以上の方が感染症への不安を抱いていることが判りました。
実際に、入浴介護によって感染した経験のある従事者は3.5%とごく少数でしたが、入浴介護の中でも訪問入浴サービスの利用者は要介護度が高く、抵抗力も減弱しているため、褥瘡をもつ人は珍しくなく、MRSAの保菌者をはじめ、肝炎や疥癬の方も散見されます。
こうした実情を反映して、この研修会参加者アンケートでも、不安な感染症として、MRSA…疥癬…肝炎…などを指摘した方がそれぞれ3割前後に達しました。
しかし、褥瘡が重度の利用者でも、主治医と相談しながら患部を「バーミエイド」で覆うなどをして入浴が提供できるのと同様に、感染症の利用者であっても、適切な衛生管理をすれば、従事者にも安全な入浴介護は可能です。
感染症を過度に恐れるのではなく、実践的な感染予防の知識をしっかりと備えて、入浴の機会を要介護者に確保してほしいものです。
入浴介護の利用者が感染症の保菌者の場合はまず、その日の最後に訪問することにして、どうしても必要な場合は、利用者や家族に十分な説明をしてからマスクや手袋、ガウンなどの着用を許してもらいましょう。
そして、感染症や病原体に応じて、効果的な消毒剤を選び、量や濃度などにも十分に注意をして業務を行う必要があります。
入浴介護が終わったら、浴槽等の物品類は、「サニーバスターS」等で洗浄します。タンカネット等の繊維材質のものは、持ち帰り「ローパス洗剤」等を使用し洗濯機で洗浄します。
通常はこれらの処理で洗浄と必要十分な除菌ができます。
MRSAや緑膿菌に汚染されている場合、浴槽は前記処理の後、高濃度エタノール含有の「サポステ」等で清拭します。ネットは「ローパス洗剤」と「ジアノック」を併用して普通に洗濯してOKです。
肝炎患者に限らず血液に汚染された場合、次亜塩素酸ナトリウム製剤である「ジアノック」等で浴槽は清拭、ネットは浸漬した後、「ローパス洗剤」で洗濯します。
手指は、通常は「シャボネット ユ・ムP-5」等で洗うだけですが、感染症対策には、エタノール含有の「ヒビスコールS」等を使用すると万全です。
入浴介護は、始めから終わりまで衛生管理が不可欠です。
入浴介護の感染防止に関わるご質問や使用薬剤などは、デベロまでお気軽にご一報ください。
※発行当時の原稿をそのまま掲載しております。何卒ご了承の程お願い申し上げます。